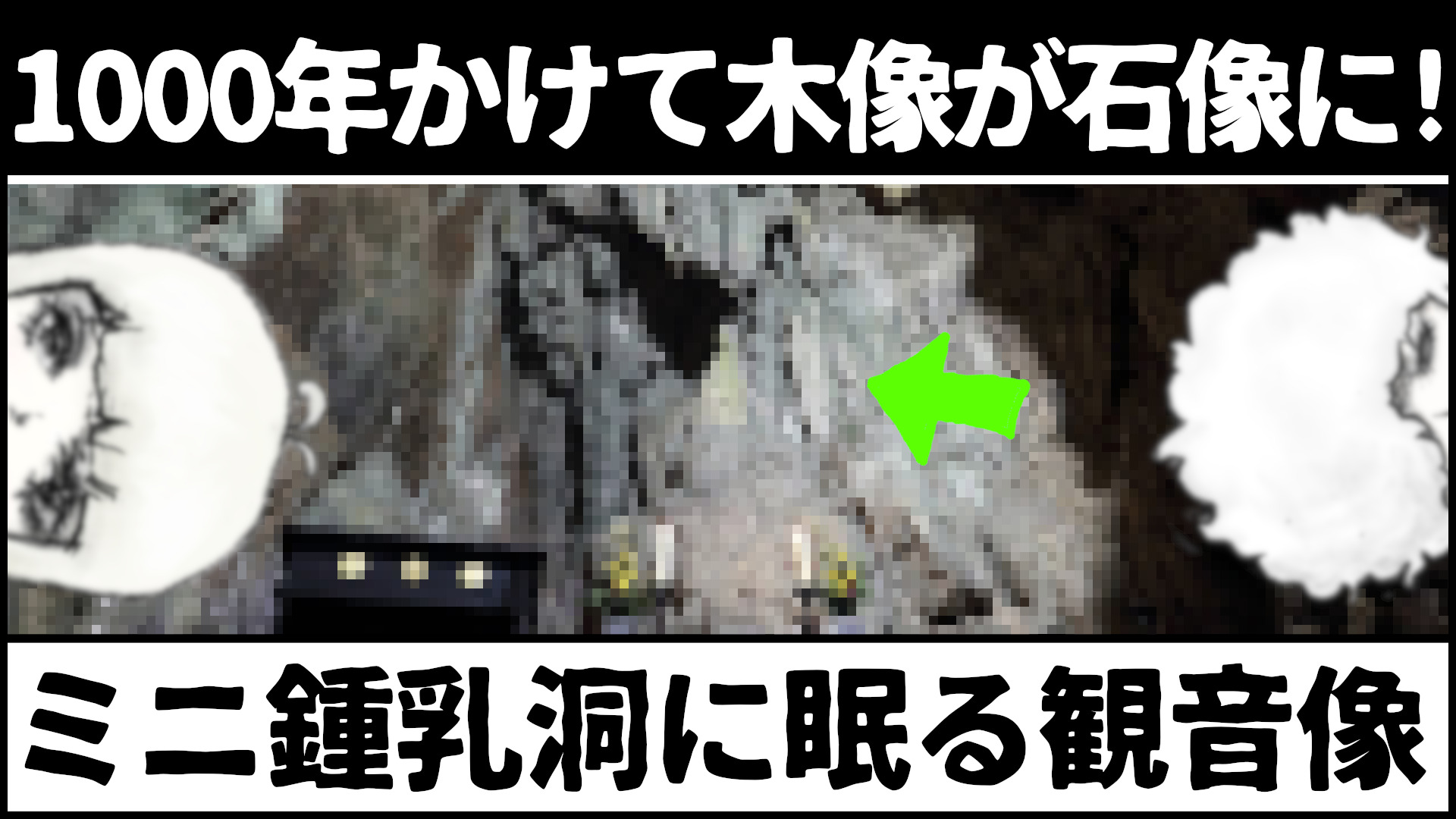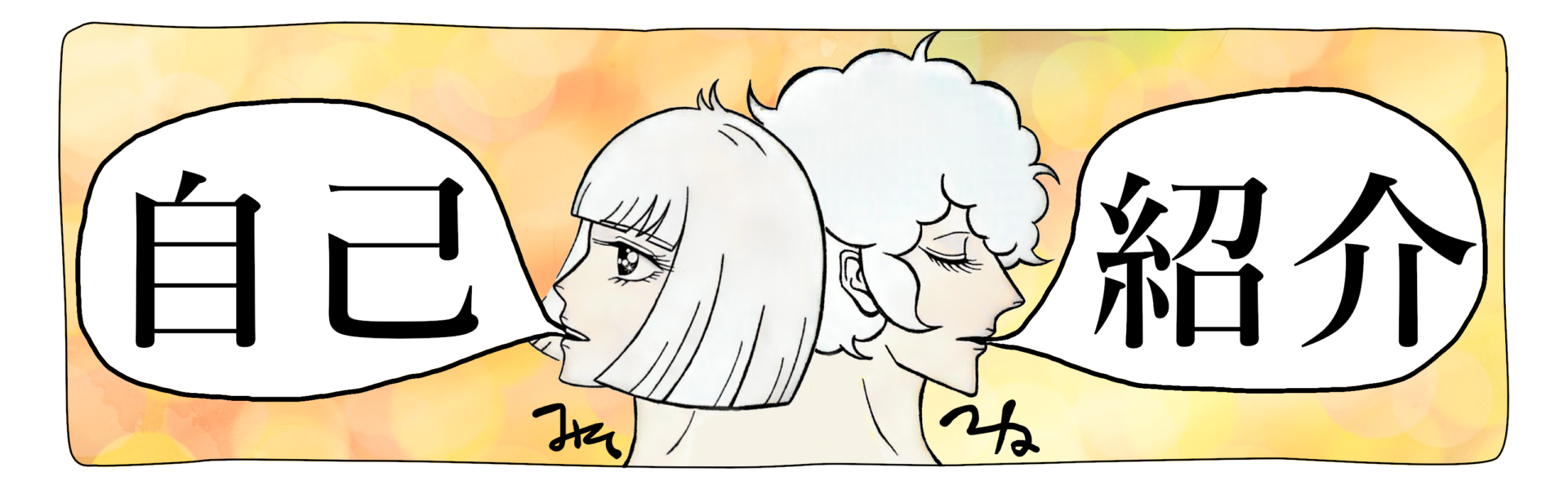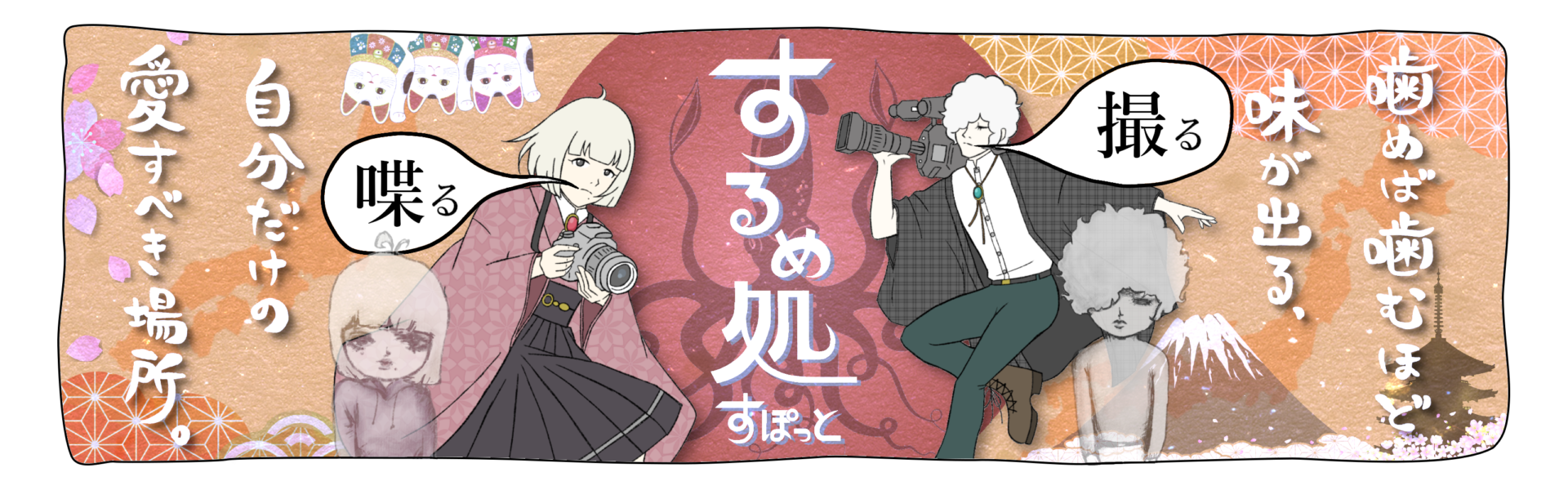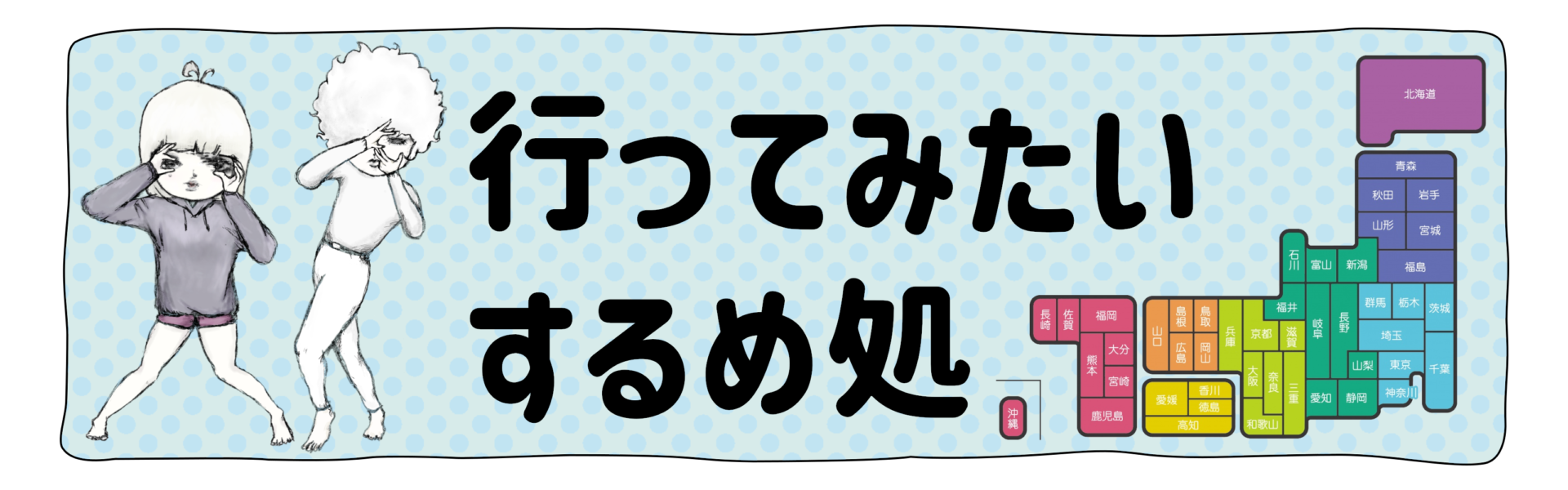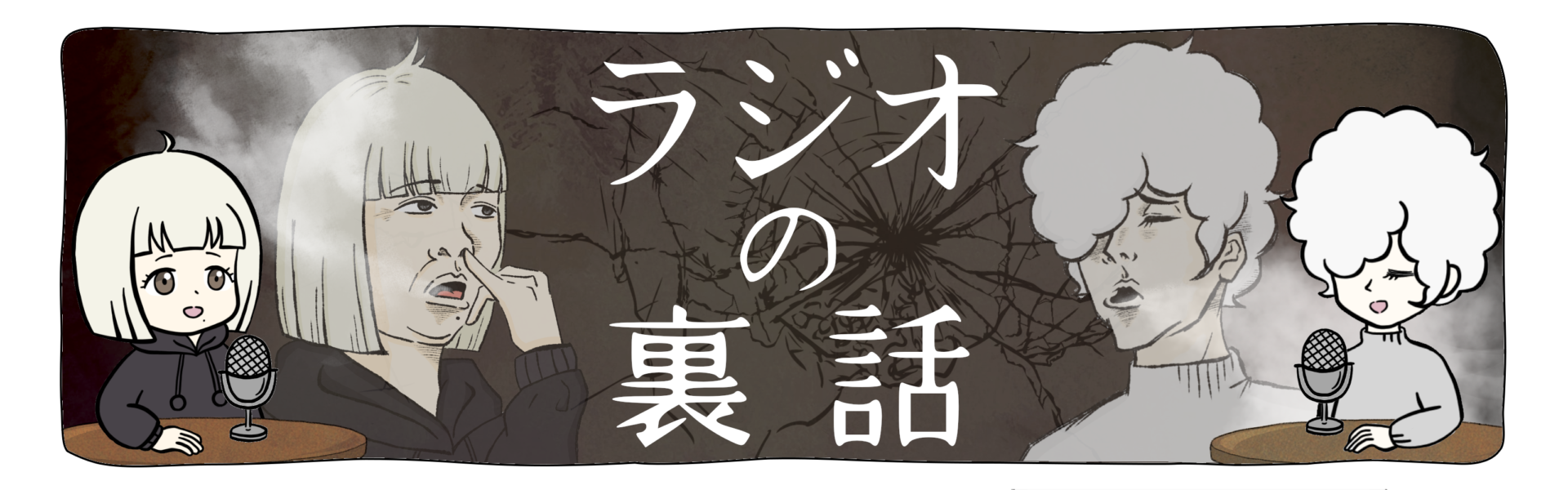※入り口付近のストリートビュー↑
今回の【つくねが行ってみたいするめ処】は岩屋観音窟という鍾乳洞です。
前回の記事【巨大水車でかまるくん】から奥に少し行ったところにあるので、前回の続きみたいな感じです。
まずこのでかまるくんや観音窟がある山口県岩国市美川町はここです。
特徴はなんと言っても江戸時代から続いた鉱山です。タングステン、銅、錫、銀、などが採れました。1993年にすべて閉山してますが、そこはちゃんと再利用。閉山した鉱山を地底王国としてテーマパーク化しています(美川ムーバレーの記事↓)。

またこの町を流れている錦川の本流&支流にはあの美声で鳴くことで有名なカジカガエルが生息しています。風流極まれし。→【カジカガエルの鳴き声(YouTube)】
そんな美川町に遠く離れた地から人知れずグッときてる私つくね。
さて今日の本題である岩屋観音窟はそんな美川町にあるいわば聖域です。
ここでジャブを。
この岩屋観音窟は鍾乳洞です。シュッ
仏像ありますシュッシュッ
国指定天然記念物です。シュッシュッドーン
奇跡起きましたバターン
てことで、今回の記事はちゃんとしてます(オイ)。
まず。鍾乳洞ってそもそも何なのさ?をおさらい。
鍾乳洞っていうのは、ざっくり言うと石灰岩が溶かされてできた洞窟。
ここでのポイントは石灰岩。
セメントなんかにも利用されている身近な石なんだけど、主成分が炭酸カルシウムでできているので、酸性で溶ける。
だから弱酸性の雨や地下水などに長年侵食されるとあんな特徴的で神秘的な洞窟ができあがるのです。
ちなみに溶けたやつがポタポタ垂れて上から伸びたものを鍾乳管。
下に垂れたものが盛り上がって上に伸びたものを石筍。
それらが繋がったものを石柱と言います。
別に覚えなくてもおおぉで良いと思います。人生どんとしんくふぃーるです。
で。
約一億5千年前に堆積してできた石灰洞である岩屋観音窟ですが、鍾乳洞自体は実は小さくて、奥行き13m、幅は約2〜5m、高さは11m程しかありません。
ただその奥に安置されている木造の観音像がパないです。
観音像の画像はこちらから↓
岩国公式観光WEBサイト【岩国 旅の架け橋】様
ふおぉ……!
この観音様は、かの弘法大師が諸国を巡礼した際にこの地に足を止め、一刀三礼して観音像を刻んだと言われています。
で、安置された観音像。どこに置かれたかというと鍾乳洞の中。上から雨やら地下水やらで溶かされた炭酸カルシウム的な液体が降り注ぎ……。
1000年後。
木造がすっかり石像になってるではありませんか!
なんという奇跡。
で、時は江戸時代。
このことを藩主である毛利綱広が知って、「この観音様を守護すんぞるぁああ」
→その前に岩屋山護聖寺が建てられた。
そして昭和9年「あれやっぱすごいから天然記念物にしない?」
→なる。
※現場の説明板に書かれている内容のふんわり要約です。
いやもう木像が途方もないような長い年月かけて石佛になるとか。浪漫がね。
そしていろいろ現代の感覚からすると結構イミフな流れ。
立ち寄ったところで「よし!観音様彫ろう!」も。
その木が腐らず石コーティングされるのも。
それを護るためにここに護聖寺!も。
わりと規格外。惹かれる。
で、さらに岩屋観音窟には別の洞窟に奥の院もあり、そっちは結構わんぱくなルートっぽいです。
下はその奥の院の口コミ。
・ライト必須。
・15mくらい進むと開けた空間に観音像あり。
・その観音像の奥にも進めるがそこからはガチルートで自己責任。
・おすすめはしない。
フムフムなるほど。
絶対行きたいやつね。
というわけで今回は岩屋観音窟でした。
次回はまたまたお隣の美川ムーバレー。いやほんと美川町最高か。
∞つくね∞