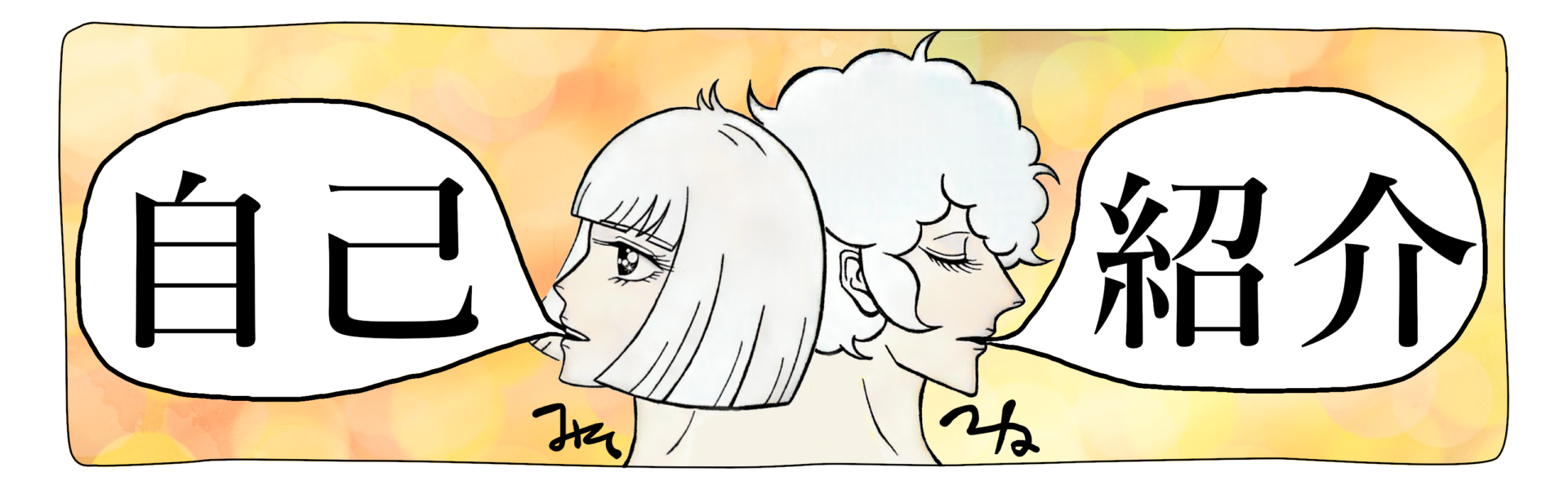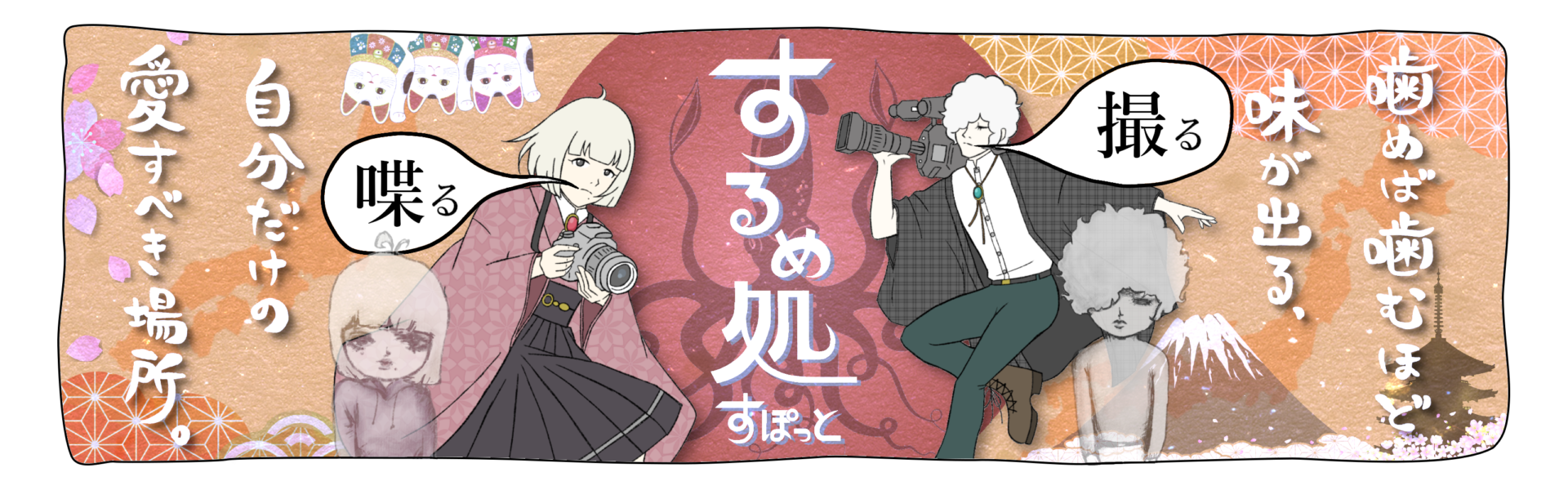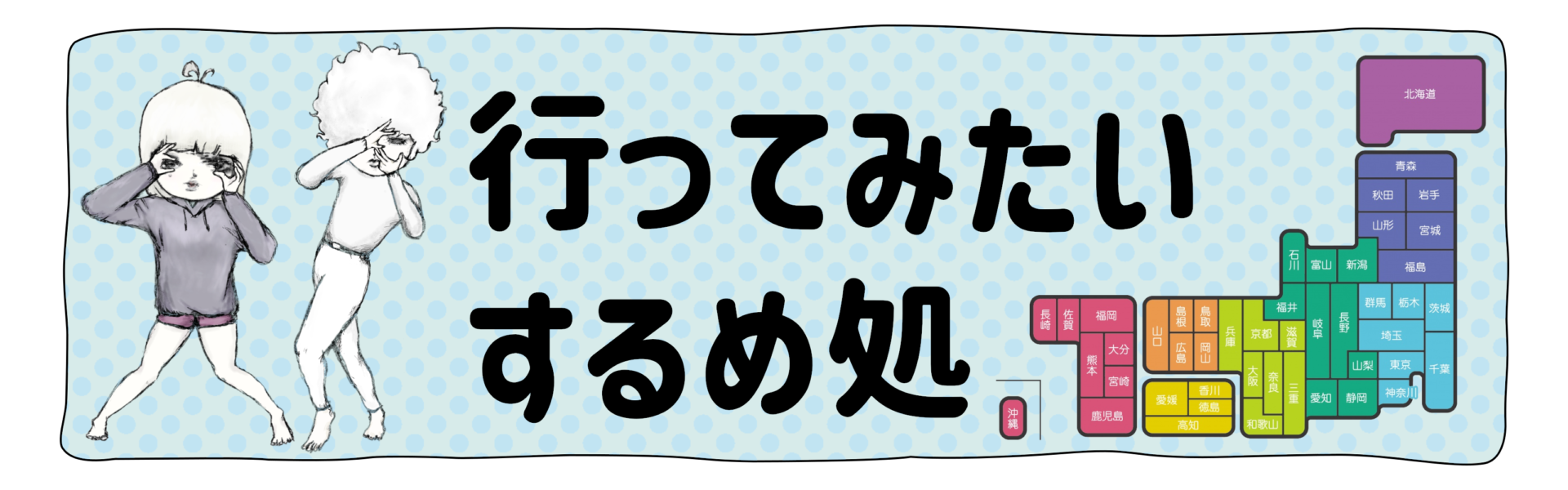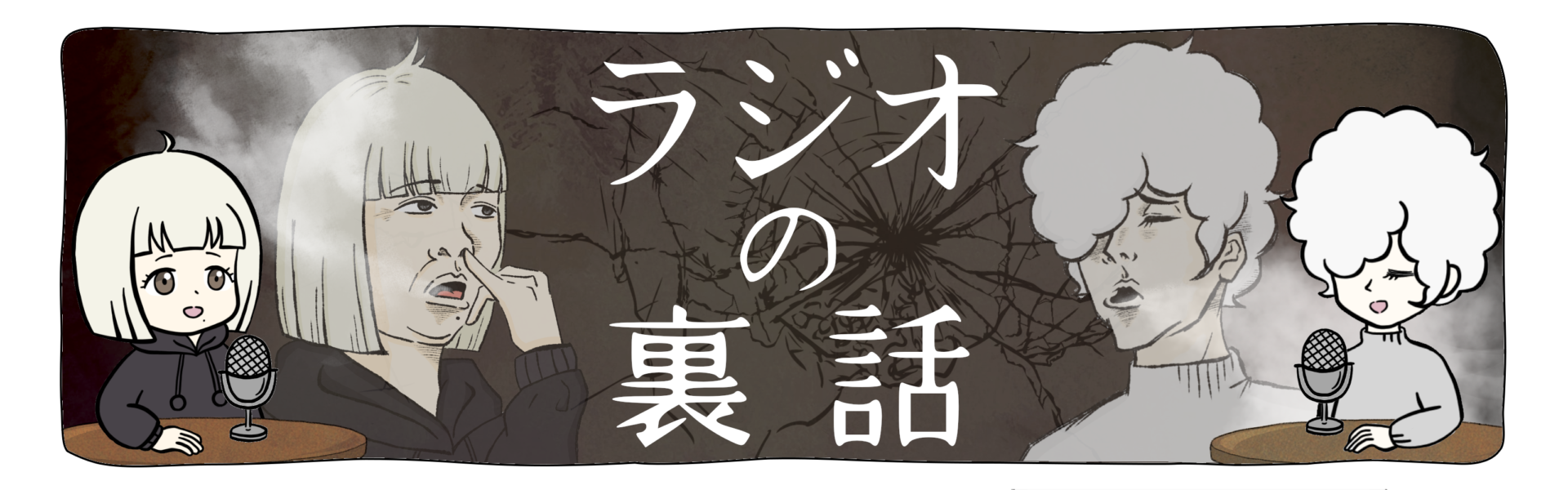前回は毘沙門天浜の記事を書きました。
神奈川県の三浦に貝殻の白浜があるなんて!
とても良き穴場でした↓↓

で、今回はその続きです。
なんとそんな毘沙門天浜に……
洞窟がありました。
しかもいわくつきの……?
ということでいってみましょう。
毘沙門洞窟弥生時代住居址群です。
場所はここ↓
毘沙門天浜から西に向かって海岸沿いを歩いていくとあるこちら。
この洞窟までの道が本当に良い。
何度でも言うけど本当に良い。
この貝殻を踏みしめるザクザク音やみつきになる。
で、こういう場所を歩いてるとついつい貝殻やらなんやら探してしまう。
で。
ふむ。
なるほど。
この弥生洞窟住居群説明すると。
人口の洞窟ではなく海蝕洞窟。つまり波や風雨などの自然の力によって掘られた自然洞窟。
横須賀の隣りにある三浦には軍事遺跡がたくさんあって防空壕や洞窟陣地が多いので、てっきり人口的な洞窟かと思いきや意外。
で、この洞窟はA・B・C・D・Eと五穴ある。住居群だからね。
歴史はめちゃくちゃ古く名前の通り弥生時代から平安時代までのとても長い間住居、そして墳墓として利用されていたそうな。
なんでそんなことがわかったのかというと、この洞窟から弥生時代の魚介類を収穫する時に使った鉄、青銅、鹿角製の銛、貝の包丁、腕輪などの装身具まで出土したから。
食べた後の貝や魚、獣類の骨も出てきたし、動物の骨を焼く占い(骨ト)で使われたト骨も出土。ここでは主に鹿の骨だったらしい。
これはもはや。
プチ貝塚なのでは。
で。
上で書いたように墓地としても利用していたらしく、C・D洞穴からは人骨も出土されている。岩壁の窪みに人骨片をおさめた墓もあるという噂。
いや。
怖えよ。
人骨に関しては家に帰ってきてから知ったよ。引いてるよ。
で、ここまで読んだくれた方は、なんとなくでも結構大きな洞窟をイメージしてるんじゃないかな。
はてさてどうかな。
さてこれ。
どうしたもんか。
くっつき虫40個程ついたよ。
よし中を見てみよう!
と思ったらここで事件が発生して。
我パニックになっちゃって。
かなりでかめの巣があったみたいで蜂が大量発生してて。
で、私つくね氏は虫や爬虫類全然ウェルカムなんだけど、身に危険を及ぼす可能性がある存在は大嫌い。
毒蛇、ムカデ、ヒル、そして蜂。
特に蜂は昔、崖に登ってて蜂の巣を鷲掴みして追いかけられて頭に同時に2発食らってから結構な苦手意識となってて。
で、弥生洞窟住居群。
なんか知らんがアシナガバチが大量にいまして。いや本当に大量に。
0コンマ何秒かで心折れて慌てて出口までボルトした。
でも。
冷静に考えて。
動画にしないまでも。
このブログに書く時に。
写真ないとか。
くっっそ冷める。
頑張れと。
自分頑張れと。
これがスズメバチなら帰る。
だがおまえ。
アシナガバチだろ?
お前今年の正月の初詣で今年は頑張る的なことほざいてたろ?
突入!
刺激しないようにゆっくりと。
近すぎる耳元の羽音を気にせずゆっくりと。
でもこの洞窟不思議な感覚だった。
なんというか、別に暗くもないしおどろおどろしい雰囲気もないんだけど、特別な空気感。
ここを訪れた別の人のブログとかでは不気味とかも書いてあったけど、そこまでは思わなかったけど不思議な感覚だったかな。説明下手ですまん。
で、洞窟の奥は段々と細くなってて、人が入れないほど細くなってて。何があるんだろうとフラッシュ炊いたりしたけど、どうやら行き止まりっぽい。
感想。
狭い。
この洞窟思ったより狭い。
入り口幅は約6m。
奥行き約17m。
でこの狭さを体感した後に思うわけです。
弥生時代はわかる。
雨風しのげて漁にも秒で行ける距離で利便性あって。
でもこの洞窟が平安時代まで人が使用し続けて、なんならお墓にまでなってたという事実。
不思議。
弥生時代に骨トまでされてたことから、この土地のエネルギー、または気&オーラ的サイヤパワー風な何かしらがあってそれが人を引き寄せて、そのマインドや風習が後世まで脈々と受け継がれていたっていうのは妄想しすぎ?
今は無いけど、以前は神仏に関わるものが置かれていたり、祈りの場だったとか、何かしらの【信仰】が絡んでるとかはいきすぎ?
あと別の妄想としては……
弥生時代はバリバリ住居として使われていたけど、平安近くになってからは完全にお墓として使われていた説。しかも無縁仏的な共同墓地として。
個人的にお墓ならそれに纏わる置物、彫物、装飾がありそうなのにそれもない。
あったのに無くなったのかそれとも……だってこの狭さの殺風景な洞窟に人骨出てくるってさ……。
なんていう妄想をするのも遺跡をたどる醍醐味だったり。
とりあえず。
この記事の画像に人の顔とか変な影とかあっても本当に知らせないで頂きたいし、それは顔じゃないし、顔だとしてもきっと応援してくれてるだけです。怖がりです。よろしくお願いします。
∞つくね∞